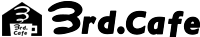オーナーブログ「きりたにのひとりごと」
「ロングライフ」住宅
住宅におけるロングライフというコトバの意味は多岐にわたっているのですが、
たいてい「基礎、構造がしっかりしていて長持ち」なのです。苦笑
というカンジで今日は本当のロングライフの意味を考えてみませんか_
日本という国は、関東大震災、第2次世界大戦後より以降、改めて建築文化が構築されてきた歴史があります。
明治維新後の明治大正の建築物と、震災後の昭和の建築物の違いは、そういった歴史を感じとれる興味深いものでもありますよね。
戦後、
当時の時代背景により、住宅というのは「とにかく住めればいい」
1世帯に1住宅を目標に大量に急速に住宅文化が進んでいきました。
団塊の世代の方で幼少の頃、1つの住宅に多世帯で住んでいたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
現在、
豊かになった今の時代では、住宅の質の向上、特に耐震性(関東大震災以後に続く震災も踏まえて)にスポットが当てられています。
_で、ロングライフ=「基礎、構造がしっかりしていて長持ち」という単純な思考に至るわけです。
もちろん、しっかりしているというのは大事なことでロングライフの基本の基本でしょう。
_でも、これだけで100年も200年も壊されずに建ち続けていられるのでしょうか?
・・・考えてみてください
多くの地震を経験してきて、建築基準法も改正され、
つくり手側も耐久性、耐震性の向上に弛まぬ努力を注ぎ今の技術があります。
たいていの工務店、住宅会社がつくっている現代の住宅は(欠陥住宅を除いて)
メンテナンスさえきちんと行っていけば100年なんて充分に耐えうる家でしょう。
でも、それだけで100年残っていきますか?
建て主よりも長生きする家なのです_
お子さん、お孫さんが大切にしてくれるでしょうか_
100年後の生活習慣にも合致できる家なのでしょうか_
100年後も住みたい家なのでしょうか_
100年後も愛してもらえる、家族の思い出がつまった家なのでしょうか_
100年後も家族がしあわせでいられる家でしょうか_
いま、みなさんがつくろうとしている家はご夫婦だけの家ではないでしょう_?
その後の世代に受け継がれていく、ご家族の家なのです_
ごく普通の・・・こんな考え方、価値観が日本に根づいていけば、これからの建築文化や住宅文化は欧州に近づいていくことでしょう
小さいからわからないだろう_ではなく、お子さんに聞いてみませんか_?
「この間取りはどうだい?おまえたちの部屋はここでいいのかい?」
_やがて
お子さんは大きくなり、お孫さんに愛情を込めて言うんじゃないですか_?
「この家は爺さん、婆さんと、父さんでつくった家なんだよ。」_と